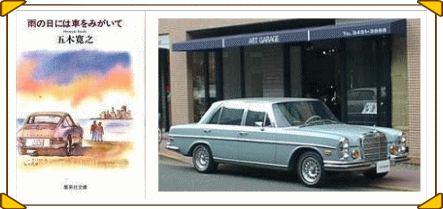
| 人には誰でも大切なものがある。それは得てして、他人にはつまらないものであることが多い。例えば、小さな子の薄汚れたタオルのように、あるいは薄汚いぬいぐるみのように。 でもそれは現実的なものであると同時に、夢やあこがれでもあるものだ。僕にとっての車とは、正にそういうものであると言えるだろう。 そして、その時々に好きになってしまった女性たちもそうなのかもしれない。決して彼女たちをけなすわけではなく... その車は、1968年にシュツゥットガルドで生まれている。1972年までにわずか6,500台ほどが生産されただけだった。この一見何の変哲もない4ドアセダンが、実は《不気味にさえ思えるほど》のパワーを秘めているのだった。わずか2,800回転で51Kg/mのトルクを発生させ、SS1/4マイル14.5秒と言うテストデータさえある。 そんなことを知っているドライバーは、バックミラーに〈タテ目〉を見つけたら道を譲ることだろう。そして、この車をあのグロッサーの孫娘と僕は心の中で呼んでいた。 ある日僕が知りあったのは、地方の豪商の孫娘だった。と言っても、祖父の代は大したものだったらしいが、父親の代ですべての財産をなくしてしまったらしい。 しかし彼女は、一見とても清楚で気品に満ちていた。目元が涼しく、僕の〈タテ目〉に正にぴったりだと思った。 つき合っていくうちにわかったことだが、思いこむと周りが見えなくなってしまう。まるで、アクセルを不用意に踏み込むとオートマチックのくせに後輪を空転させる〈タテ目〉のように。 でも僕は、そんな彼女にのめり込んでいくのだった。彼女と一生共に生きていけたらと思っていた。 しかし彼女が僕とつき合っていたのは、僕を本当に愛していたからではなかった。実は、僕の〈タテ目〉の前の所有者は彼女の父親であったのだ。彼女は子供の頃からこの〈タテ目〉に乗り、ある種ファザーコンプレックスの中で、次の所有者とつき合っただけだった。 そんなことがわかっても、僕の気持ちが変わるわけではない。しかし、他人から見れば「何故?」と思うことが色々あったのだと思う。 そして、結局〈タテ目〉を手放した翌日、彼女は僕の部屋から出ていった。 今思い出しても、僕にとっては大切な人だ。そして、あの〈タテ目〉も忘れることはないだろう。しかし、僕は自分がそろそろ車の遍歴から足を洗おうとしていることに気づき始めていた。 |