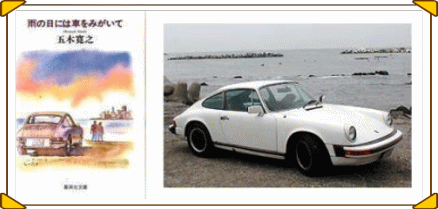
| 僕はその頃、メルセデスの四駆[300GD]に乗っていた。5気筒のディーゼル車は、わずかに88馬力しかない。しかしデフをロックしGAにシフトすると、頼もしいの一言だ。 その日は梅雨の空模様で、ワイパー越しに滲んだポルシェのリアが見えた。 私は間違っていただろうか。彼を愛し始めていた自分に驚き、そして慌てて飛びだした部屋。あれは彼が〈タテ目〉を手放した翌日だった。 大した意味はなっかったが、彼はそう思わなかっただろう。このポルシェ911Sは、友人からの借りものだ。雨の日にはもっとも不向きな車だろう。考えてみれば〈タテ目〉のビッグトルクも雨の日には余計なものだ。 余計なものでも、とっておきたいモノもあれば、どんなに大切と思っていても、手放さなくてはならないモノもある。彼にとって〈タテ目〉がそうだったのだ。明らかにファザコンの私とやっていくためには、父の面影の〈タテ目〉は手放すべきと考える生真面目さが、彼のよいところでもあった。 そんなことをぼんやり考えながら、私はハンドルを左に切った。 交差点をゆっくり左に曲がっていくポルシェを見送り、僕は青信号をまっすぐ進んだ。部屋を出ていった彼女を思い出しながら。 僕は、彼女を自分だけのものにするために〈タテ目〉を手放したつもりでいた。彼女が父親を乗り越えて行くためには、あのグロッサーの孫娘と縁を切らなくてならない。それは考えすぎだったかもしれないが、僕には自信がなかった。 他人には、世間をうまく渡っていく人間に見えがちな僕だが、見かけよりずっとシャイなのを彼女は知っていただろうか。 今となっては、どうでも良いことだけど。 さっきの後ろのメルセデスの四駆は、かつて父が持っていたタイプと同じだったろう。未だファザコンが抜けないと言うより、私の好みなのだ。そして、そういったものを好む男に引かれるのも、生まれついてのものだろう。 けれど、私は彼と別れた。確かに彼は私の好みにぴったりだった。これほど自分にあう男は二度と現れないだろう。だから怖かったのだ。自分をなくしてしまいそうで。 そして、今は自分の好みではない911Sを運転している。やがて大して好きでもない男と、平凡な結婚をするだろうと思いながら... |